第七話 黄金の雷(11)
かくして、トゥパク・アマル、彼の妻ミカエラ、長男イポーリト、末子フェルナンドの四人は、一旦、一同に、クスコ近郊の山間の地に集められた。
しかし、言葉を交わすなど言語同断、まともに顔を合わすことさえ許されぬままに、冷酷にほくそえむスペイン軍総指揮官アレッチェの監視下の元、そのまま、かつてのインカ帝国の旧都クスコへと引き立てられていった。
道中のトゥパク・アマルは、戦闘時に身につけていたままの金糸の入った黒ビロードのマントを纏(まと)っていたが、胸に提げていた黄金の太陽神像は取り去られ、代わりに黄金の十字架とキリストの像を鎖でかけられていた。
また、騎馬ではあったが、足枷(あしかせ)をはめられていたため、馬に跨(またが)ることができず、女性のように横乗りにさせられていた。
その彼の後方には、鞍無しの白ラバに乗せられたミカエラが、そして、やはりラバに乗せられたイポーリトとフェルナンドが続く。
彼女らもまた、捕われた時のままの服装で、しかも、顔を隠すことを許されぬという理由から、帽子を被ることもかなわなかった。
そのような姿で、彼らは、1781年4月16日、ついに、かつて激戦を交えた牙城クスコへと入ってきたのである。
スペイン軍は、インカ帝国時代の神殿を取り壊して築いたサント・ドミンゴ教会から兵営までの、延々と続く道の両端に仰々しく隊列をなし、アレッチェに先導されながらクスコに入ってくるトゥパク・アマルらを、険しい眼(まなこ)で見据えている。
そのサント・ドミンゴ教会の高窓からは、この国のカトリック教会最高位の司祭モスコーソが、あの舐(な)めるような視線をいよいよ炯炯と光らせながら、囚われたトゥパク・アマルたちを見物しようと、いかにも満足げに眼下を睥睨(へいげい)していた。
そして、スペイン軍の背後からは、スペイン渡来の白人の市民たちが、トゥパク・アマルらの姿を好奇の目で覗き見ている。
一方、囚われのインカ皇帝が引き立てられてくる悪夢のような情景など、全く、見るに耐えぬインカ族の者たちは、皆、家に深く引き篭もり、道端には、一切、彼らの姿は見られなかった。
故に、街中に姿を現しているのは、兵にしろ、市民にしろ、完全に白人のみである。

しかしながら、彼ら白人たちの目にさえ、今、目前を通り過ぎていくトゥパク・アマルたちの姿は、彼らが予測していたような惨めさなど、欠片も感じさせぬものだった。
トゥパク・アマルは常のごとくに、今、この瞬間も完璧に落ち着き払っており、これから牢につながれる身であるなどという気配を微塵も感じさせぬどころか、まるで、これは勝利の凱旋かと見まがうほどに、威風堂々たる雰囲気を放っていた。
彼は、きっぱりと精悍な顔を上げ、その凛々しく美しい切れ長の目で真っ直ぐに前方を見つめ、インカの都を吹き過ぎていく秋風に緩やかに漆黒の長髪をなびかせながら、進み来る。
馬に横乗りにさせられていようが、足枷をされていようが、幾多の戦闘によって逞しく日焼けした褐色の肌を翻(ひるがえ)るマントから覗かせながら、凛と背筋を伸ばして座すその姿は、まるで玉座にいるかのごとくに、厳かな優美さと強い存在感を放っていた。
黄金色に輝く太陽の下、このインカの旧都で待ち侘びていたインカの父祖の霊たちが、彼のクスコへの帰還を懐を広げて出迎え、守護してでもいるかのように、トゥパク・アマルの周りには光が集まり、神々しい覇光が立ち昇る。
スペイン兵にしてみれば、この反乱で彼らを震撼させ続けてきたトゥパク・アマルは憎んでも余りある存在であり、にもかかわらず、今、眼前を通り過ぎていくその人物は、どれほど否定したくとも、彼らの目にさえ、まぎれもなくインカ皇帝そのものに見えてしまう。
他方、クスコの街を進み来るトゥパク・アマルを、アドベ(日干しレンガ)造りのささやかな家々の中からそっと仰ぎ見ていたインカ族の者たちは、彼の姿を垣間見た瞬間、悲愴さなど完全に忘れ去り、恍惚たる表情で「やはり皇帝陛下…!!」と感嘆の声を洩(も)らし、そのまま跪いて深く礼を払った。
此度のトゥパク・アマルの捕縛を知らされて以来、再び深く自尊心を傷つけられ、いっそう身を縮めていたインカ族の人々の胸に、今再び、インカの末裔としての誇りが熱く甦る。
トゥパク・アマルの来訪によって、クスコの街全体の空気そのものが変化し、インカ時代の輝きを急速に取り戻していくようでさえあった。
そして、トゥパク・アマルのみならず、彼の後方から進み来る、囚われの彼の妻ミカエラも息子たちも、トゥパク・アマルに劣らぬ凛とした毅然たる風貌で、まさにインカ皇帝の妻、そして、インカ皇帝の息子たちに相応しい気配を放っている。
ただでさえ絶世なる美貌のミカエラは、常日頃から人目を惹きつけずにはおかないが、潔い覚悟を宿した研ぎ澄まされた眼差しに、囚われのその姿には深い憂いをも纏い、まるで神話の挿画のごとくに現(うつつ)離れした麗しさを醸し出していた。
そして、その二人によく似た、まるで凛々しく純真な天使のような光を放つ息子たち…――。
そんなトゥパク・アマルら家族たちが過ぎる度に、街道沿いのスペイン兵たちからまで、次々と恍惚の溜息の漏れるのを、陣頭に立つアレッチェは、ひどく苦々しい気分で眺めやる。
(ついに悲願であったトゥパク・アマルを捕え、晒(さら)し者にしているというのに、この空々しい気分は何なのだ…!)
そして、やはり、この光景に、アレッチェと同じ苦い思いを噛み締めている、もう一人の人物がいた。
サント・ドミンゴ教会の高窓から眼下を覗き見るモスコーソ司祭もまた、アレッチェ同様に、先程までのしたり顔をにわかに引きつらせていた。
そんな己の様子を周囲の目から隠すようにして、彼は肥満気味な手で顎の辺りを不自然に撫でている。
アレッチェは苛立ちを露(あらわ)にした眼でトゥパク・アマルを一瞥すると、一団に号令を発して、幽閉先には直接向かわず、わざわざ処刑場へと立ち寄らせた。
処刑場に定められた広大な広場の中心には、トゥパク・アマルらが、やがて刑を執行されるであろう処刑台が、まだ刑の執行日が何日後になるのか、あるいは、何週間後になるのかさえ定まらぬというのに、既に、しっかりと準備されている。
この方法、つまり、事前に、公衆が大勢集まっている面前で、「罪人」たちに、わざわざ処刑場を見せるといった、このやり口は、当時の宗教裁判の常套手段でもあった。
アレッチェは、トゥパク・アマルら家族を、敢えて処刑台の傍まで寄せて見せつけながら、横目で、その反応を窺(うかが)う。
だが、トゥパク・アマルもミカエラも顔色ひとつ変えぬばかりか、まだ幼い息子たちでさえ、悟ったように落ち着き払った表情を全く変えようとはしなかった。
アレッチェは目元を引きつらせ、酷い侮辱感さえ覚えながら、無言のまま憎々しげに地面に唾を吐く。
(その痩せ我慢、いつまで続くものか…今に思い知るがよい…――!!)
実際、この頃には、スペインの宗教裁判は一連の形態を確立しており、この後、トゥパク・アマルらに加えられるべき拷問の方法も道具も、処刑台同様に、幽閉先には、この時点で既に準備されていたのだった。
兎も角も、この日、そのままトゥパク・アマルら家族たちは、幽閉先である、当時、スペイン側の兵営に使われていた旧イエズス会の修道院へと連行されていった。
修道院の地下に設けられた牢に通じる門前で、アレッチェは、彼らがそれぞれバラバラに収容されること、そして、次に互いの顔を見るのは処刑の日であること、それをあの氷のような冷血な口調と表情で射すように言い渡す。
それでも、トゥパク・アマルたちは、表情を変えはしなかった。

だが、本当の彼らの心中は、果たして、いかなるものであったろうか。
推察するしかないことではあるが、末子のフェルナンドは、この時まだ8歳…――暗黒の冷たい牢獄を前に、フェルナンド自身の覚えた恐怖のいかほどに強かったことか。
そして、この幼い息子、あるいは弟の心中と今後のことを案ずる、父トゥパク・アマルの、また、母ミカエラの、兄イポーリトの心は、実際には、どれほどに、いたたまれぬ思いに苛(さいな)まれ、激しく掻き乱されていたことであろうか。
しかし、彼らは、今、それを決して表に出すことはなかったのだった。
果たして、その頃、トゥパク・アマルとミカエラの次男、10歳のマリアノは、一体どうなっていたであろうか。
敵の追っ手の目をかすめるため、マリアノは、母ミカエラと二人の兄弟とは別行動をとっていた。
そのマリアノは、幸運にも、まだ敵の手中に落ちることなく、今のところ順調に避難を続けていた。
彼は貧しい平民に扮し、トゥパク・アマルが全幅の信頼を置く重側近たる老賢者ベルムデスと、そして、やはり平民に扮して影武者のごとくに付き従う敏腕の護衛官たちに堅く守られながら、何も不審なところは無いという素振りで、敢えて堂々と街道沿いの町や村を通過しながら進んでいた。
目指すは、ラ・プラタ副王領で勢力を維持しているアンドレスの陣営である。
だが、頑強な大人の足でさえ何十日も要する隣国ラ・プラタ副王領までの道程は、幼い子どもと老人の足には、気が遠くなるほどに果てしなきものであった。
しかも、今や彼らは、この国で最たる「お尋ね者」として、国中のスペイン役人たちから追われる身である。
いつ、どこから、敵襲に遭うかも分からぬという、全く予断を許さぬ、常に神経を張り詰めた過酷な旅である。
その厳しい逃亡の旅の道程は、十数日間を経ても、なお、目的地には遠く及ばぬものであった。
そして、情報網の限られているこの時代、旅を続ける彼らは、別ルートで逃亡を続けているはずのミカエラやイポーリト、フェルナンドが、囚われたことさえ、まだ知らずにいた。
そんなある日の夕刻時、目指すラ・プラタ副王領に通じる街道沿いの小さな町に入って一夜の宿を定めると、ベルムデスはマリアノを伴って、宿の食堂に下りていった。
下層の庶民たちでごった返すその空間は、一日の力仕事を終えた男たちで溢れており、むせかえるような酒場の様相を呈している。
殆ど物乞いのごとくに貧しい服装をして、幾日も入浴さえしていないような薄汚い「親子づれ」の客が入ってきたのを認めると、中年のインカ族のウェイターは蔑むような視線になって足早に二人の方に近づいてきた。
「金は?
食事代を払える金は持っているのか?」
疑いの眼で年老いた父親らしき人物を一瞥しながら、ウェイターが不審の目で問う。
「へい…旦那。何とか、こちらの宿代と食事代くらいの持ち合わせは」と、わざと訛(なま)りを交えてベルムデスが応える。
まだ疑わしそうな目をしたまま、ウェイターは、傍にじっと佇んでいる10歳前後の少年に視線を走らせた。
少年は「父親」の陰に隠れるようにして、砂埃にまみれた顔を俯(うつむ)き加減にしたまま、まるで顔を隠すように布を頭から深く被(かぶ)り、その表情は分からない。
ウェイターは、再び「父親」の方を見て、「ここは酒場同然の場所だ。子どもの入るような所じゃない」と、理屈をこねて、体(てい)よく二人を追い出そうという勢いだ。
しかし、いかなる追っ手や罠が待ち構えているかも分からぬ夜間の街中を歩き回ることこそ危険であると悟っているベルムデスは、深く身を屈めて、哀願するように続ける。
「いえ、旦那…。
どんなものでも構いませんから、何か、せがれに出してやっておくれなさい」
そう言いながら、「せがれ」の肩を掴んで、さっさと近くの椅子に座らせると、自分もその傍にしっかりと腰を下ろした。
ウェイターは鬱陶しそうな目で、もう一度、二人を一瞥した後、「やれやれ」と呟きながら厨房の方に戻っていった。
何とか席に落ち着いたマリアノとベルムデスは、小さく息をつき、改めて、食堂を見渡した。
安宿の食堂にしては、まずまずの広さを有し、夕食時でもあるためか、宿泊客よりも、むしろ、飲食に立ち寄ったらしき男たちが大勢ひしめき、結構な賑わいを見せている。
中にはスペイン人の男たちの集団もいて、酔った勢いか、酒を片手に大声を張り上げながら談笑していた。
その言葉の言い回しや抑揚のさまから、地元のスペイン人ではなく、スペイン本国から渡来したらしきスペイン人たちであることが分かる。

「あの人たち…」
マリアノが被り物の陰から警戒の目で、そちらを鋭く見渡した。
ベルムデスは集団を観察していた視線を素早くマリアノに戻すと、目立たぬように頷いた。
「マリアノ様、大丈夫です。
この辺りには、ちょっとした鉱山があるのです。
ここにいる連中は、恐らく、その鉱山で働く労働者たちでありましょう。
黄金を掘り当てようと、一攫(いっかく)千金を狙って海を渡ってきた荒くれ者どもではありましょうが、かかわりさえしなければ、むこうは物乞い風情の我々などには見向きもいたしません。
さあ、あまり、あちらを見てはなりません…」
いかにもスペインから渡ってきたらしき白人の存在に敏感に反応しているマリアノを安心させようと、静かな声でそう囁(ささや)きながら、ベルムデスは穏やかな瞳で微笑んだ。
そんなベルムデスの表情に、マリアノの張り詰めた肩の力も、ふっと抜けていく。
このような緊迫した状況下にあっても、常に温厚さと包容力を失わぬベルムデスと共にあると、まるで本当に己の祖父と旅をしているような気分になり、マリアノの心は和(なご)んだ。
実際、マリアノの父であるトゥパク・アマルは幼い頃に両親を亡くしており、それ以来、このベルムデスが父親のごとくにトゥパク・アマルに寄り添い、支えてきたため、血こそつながってはいなかったが、マリアノにとって、このベルムデスは実の祖父にも等しき存在であった。
また、ベルムデスから見ても、ずっと傍近くで見守り、時にはトゥパク・アマルら夫婦と共に養育してきたマリアノは、まるで己の本当の孫のような愛しい存在であった。
どれほど泥土にまみれていようとも、今も、まるでトゥパク・アマルを少年時代に移し替えたかのような、褐色の天使さながらに美しく愛らしいマリアノの顔を見つめていると、ベルムデスの胸は熱くなる。
彼は、60歳も半ばほどまで年輪を重ねてはいたが、つい先日の本陣戦でも、現役で戦線に立って武器を執(と)っていた。
優れた徳と知恵と武芸とで王族を助けながら、この厳しい時代を生き抜いてきた彼は、厳(いか)ついその手で、今は、優しくマリアノの被り物の角度を整える。
そして、目元に皺を寄せ、目を細めながら静かな声で言う。
「マリアノ様。
どうか、お顔だけは、見られないようにお気をつけなされませ。
たとえインカ族の者であっても、あなた様の正体を悟られてはなりませぬ。
どのような形であれ、騒ぎになっては厄介です」
「うん。
わかってる」
ベルムデスの言葉に、マリアノは利発そうな瞳で素直に頷くと、スペイン人の集団に向けていた視線をテーブルの上に戻した。
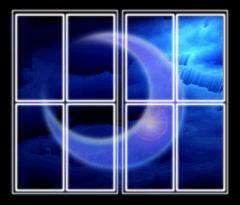
それから、マリアノは、既に暗くなった窓外に目をやると、今頃、やはり別のルートを通りながら同じ目的地に向かっているはずの母や兄弟たちに思いを馳せた。
さらに、次の瞬間には、彼の脳裏に、父トゥパク・アマルのことが飛来する。
インカ全体に向けるのと同じほどの、大きく深い愛を、自分たち息子たちにも向けてくれた父トゥパク・アマル…――しかし、まだ10歳の、しかも、この過酷な逃亡下の皇子マリアノにとって、囚われた父のことを思い出すことは、まだあまりにも、きつ過ぎた。
彼は意識的に父のことを考えまいとして、母のこと、そして、兄弟たちのことに、懸命に思考を戻そうとする。
そんなマリアノの苦しげな横顔を、そっとベルムデスが見守っている。
そして、彼もまた、トゥパク・アマルのことに、次いで、ミカエラや彼らの他の二人の息子たちのことに思いを馳せた。
ベルムデスの表情にも、深い苦渋が滲む。
(トゥパク・アマル様は、今頃は、もう既にクスコの幽閉先に行かされているかもしれぬ。
ミカエラ様やご子息様たちは、今頃、どうしておられるであろうか。
せめて、母上やご兄弟がご無事であられることだけでも知ることができれば、マリアノ様も、どれほど、ご安堵なされることか…)
まだまだ情報網の未発達なこの時代、それぞれに別れて行動している者たちの動向は、容易には掴み得なかった。
この時点では、まさかミカエラたちまでが囚われているとは知らぬベルムデスは、その無事を、心底、祈らずにはおられない。
その時、不意に厨房の方から、「おい、小僧!!」と、こちらの方に向かって荒っぽい声がした。
ハッと我に返って、マリアノとベルムデスが見やった視線の先では、先ほどのウェイターが厨房のカウンターから顔を出し、皿を片手に「おまえ用につくってやったから、取りに来い!!」と、大声を張り上げている。
咄嗟のことに、マリアノは澄んだ瞳を見開いて驚いたようにそちらを見ていたが、そんな彼にベルムデスは穏やかに微笑んだ。
「あの者、何だかんだと申しても、マリアノ様の料理を用意してくれたようですな。
すぐに、取りに行って参りましょう」
そう言って、にこやかに席を立ちかける。
「いえ!
僕が言って参ります。
高齢の父親に取りに行かせるなんて、かえって怪しまれてしまいますもの!」
マリアノは、やっと少年らしい闊達な笑顔を見せると、改めて被り物を整え、周囲の視線を避けるようにしながら厨房に向かった。
チューニョ(じゃがいもの乾物)を浮かせた、ささやかなスープのようなものをカウンターごしに受け取るマリアノに、ウェイターが「それしかないから、こぼすなよ」と、無愛想に言う。
その時、皿を受け取りながら少し上向き加減になった少年の被り物の陰から、チラリとその素顔が見える。
その瞬間、ウェイターは息を呑んだ。
ボロ布を纏(まと)ったような貧相な姿とは、あまりに不釣合いな、気品溢れる、輝くような美しい容姿…――いや、目の錯覚か?!…――と、ウェイターは思わず目をこする。
彼はカウンターから身を乗り出すと、無遠慮に覗き込むようにして、被り物の陰から僅かに覗くマリアノの横顔を、喰い入るように見据えた。
一方、マリアノは、ウェイターの目線を瞬間的に感知し、サッと深く下を向くと、皿を手にしたまま素早く踵を返した。
マリアノの動悸が、速まる。
(あのウェイターに、顔を見られただろうか…?
何か、感づかれたか?!)
背中にウェイターの強い視線を感じ、内心動揺しながらも、マリアノは何事も無かったような足取りでベルムデスの待つテーブルに向かう。
ベルムデスも、ウェイターの驚きを露(あらわ)にした目つきを察知し、険しく慎重な眼差しになって、じっとマリアノを見守っている。
そんな中、マリアノが、ちょうど先刻のスペイン人の男たちの脇を通り過ぎようとした時だった。
一人の男の言葉が、マリアノの耳に響く。
「あの反乱の首謀者トゥパク・アマルの妻と、それから、やつらの息子どもが、捕まったらしいぞ」
(え…――?!
え?!!)
突如、マリアノは何かに打たれたようにビクッと全身を震わせ、愕然と、そこに凝固した。
傍らで凍りついているマリアノをよそに、酒の入ったスペイン人の男たちは、がなり立てるように大声で話し続ける。
「ああ、俺も聞いた。
惜しかったよな、実際。
そのミカエラって女にも、ガキどもにも、もの凄ぇ額の報奨金が懸(かか)ってたからな。
この萎(しな)びた鉱山町じゃあ、今更、ろくな黄金なんて出てこねぇし。
いっそのこと、本気で罪人どもを探しに行って、俺サマが捕まえたかったぜ。
そうなりゃ、今頃、本物の大金を掴んで、さっさと国に帰る支度でもしていたさ。
こんなご時世じゃぁ、掘り尽くされちまった黄金なんて、ちまちま探してるより、お尋ね者の賞金狙いの方が、よっぽど効率のいい一攫千金ってやつだ。
ちっ…!」

「くく…まあ、そう言うな。
庶民ごときが、そうそう簡単に捕まえられる相手じゃなかろう。
結局、ミカエラや息子たちを捕えたのは、軍隊の兵士たちだったらしい。
…――とは言っても、確か、まだ次男のマリアノは逃走中だと聞いたぞ。
その次男にも、目が回るほどの多額の賞金が懸っている。
だから、俺たちにも、まだチャンスはあるってことだ。
うまいこと捕えられれば、一生、左団扇(ひだりうちわ)の豪遊生活も夢じゃない」
そんなふうに冗談と真剣の混ざった面持ちで面白そうに話していた男たちの一人が、グラスを弄(もてあそ)びながら、今度は、やや趣を変えた声色で言う。
「それで、そのミカエラっていうのが、かなりの美人らしいぞ。
今頃、クスコの牢の役人たちは、さぞ、いい思いをしていることだろうよ」
「ふん。
どんなに、いい女でも、所詮はインディオだ」
かなり酒の回ってきた男たちの話題は、やがてミカエラの容姿の話に移っていった。
それらは全てスペイン語のやりとりではあったが、幼き頃から、父トゥパク・アマルによってスペイン語の教育を受けてきたマリアノにとって、その会話の内容を聴き取ることなど、あまりにも容易だった。
(え…――!!
母上たちが…――何だって?!!)
マリアノの心が叫び声を上げた時には、彼の手の中の皿が激しい音を立てて床に落ち、粉々に砕け散っていた。
ベルムデスが目を見張った瞬間には、散乱するガラスの破片と共に、皿の中にあったスープが周囲に飛び散り、まさに、今、ミカエラの話題で沸いているスペイン人の男たちの衣服の裾を、かなりの範囲まで汚していた。
一方、マリアノは、硬直した姿勢で、男たちの傍らに愕然と立ち竦んだままでいる。
当のスペイン人たちは、憤慨した形相で、マリアノの方を荒々しく睨みつけた。
だが、今や、母や兄弟たちのことに完全に意識を奪われているマリアノには、眼前で展開していることなど全く目には入っていない。
彼は顔面を蒼白にしたまま、謝罪の一つも出ずに呆然自失している。
そのさまに、スペイン人の荒くれ男たちは、いよいよ、いきり立った。
男たちの中の一人が激しく椅子を蹴って立ち上がると、マリアノの真正面にズイッと立ちはだかる。
「なんだ、このガキ!!
謝りもしねぇでっ!!」
椅子のけたたましく倒れる音と、凄みのきいた太い男の怒声に、食堂の他の客たちも、一斉にそちらを振り返った。
男は、ゴツゴツとした、いかにも鉱山労働者らしい岩のような手で、締めるようにマリアノの襟首(えりくび)を掴んだ。
「ガキ!!
痛い目にあわねぇと分からねぇのかっ!!」
相手の凄まじい剣幕にもかかわらず、母と兄弟たちのまさかの捕縛を知ってしまったマリアノの頭は真っ白で、目の焦点も定まらぬまま、何かが喉につまったように言葉が出ない。
「このガキ…!!」と、男がマリアノの襟首をさらに締め上げた時、「うっ……!」と小さく呻(うめ)いて苦しそうに首を振ったマリアノの頭から、はらりと被り物がはずれた。
その瞬間、あの高貴で非常に端正な、父トゥパク・アマルにそっくりな顔が現われる。

その場に居合わせた誰もが、その美しい少年の風貌にハッと息を呑んだ。
ただし、いくら「逃亡中のトゥパク・アマルの息子」の話題が出ていたとはいえ、まさか、このような街中の食堂に本人がいるなどとは連想の及ばぬ客たちは、この物乞い風情の少年とトゥパク・アマルの息子とを、さすがに即座には結びつけることはできなかった。
だが、そのただならぬ美形と高貴な雰囲気に、あまりにそぐわぬ貧しい身なり…――その不釣合いぶりは、たちまち人々の疑惑の念を焚(た)きつける。
次第に、不穏な空気が漂いはじめた。
やはり平民に扮し、食事を摂る素振りをしながら、同じ空間の四隅に潜んでいたマリアノの護衛の影武者たちが、すかさず脇差しに手をかけて、立ち上がりかけた。
それを、ベルムデスが無言の手つきで鋭く制する。
そして、次の瞬間には、ベルムデスはスペイン人の男たちの集団の中に走り込んでいた。
彼は、男たちの前の床に平伏(ひれふ)すと、いきなり土下座する。
「旦那様!!
申し訳ございません!!
わしのせがれが、とんでもないことを!!」
ベルムデスは、まだ男の手に締め上げられているマリアノを、その男の手からひっぺがすように引き離すと、いきなり、マリアノの頬を猛烈な勢いで打った。
そのあまりの激しさに、マリアノの体は数メートル先の食堂の壁際まで吹っ飛んでいった。
ドウッ!!という大きな振動音と共に、マリアノの体が壁にぶち当たって、そのまま床に崩れ落ちる。
いくら高齢とはいえ、このベルムデスは、先日まで戦場で武器を振るっていた豪腕の持ち主でもある。
本気で打たれれば、10歳の子どもの体など、ひとたまりもない。
周囲の客たちまで、思わず、ビクリと身をそびやかせ、固唾を呑んだ。
他方、ベルムデスの強烈な一撃で口内を切ったのか、マリアノは唇から血を流しながら、ギョッとした目で我に返ったように、その身を起こしかけた。
だが、マリアノに立つ間も与えぬ勢いでベルムデスはマリアノの元に大股で迫り来ると、少年の胸倉を掴んで強引に引き摺(ず)り起こした。
「おまえは、旦那様のせっかくのお召し物になんてことを!!」
彼は鬼のような形相で睨みつけ、今度は少年の反対の頬を平手打ちする。
マリアノの体は、そのまま、反対の壁際まで吹っ飛んでいった。
再び、少年の全身が、激しい振動音と共に、容赦無く壁に打ち付けられて、地に沈む。
あまりの強打のために、腫(は)れ上がった顔をガックリと床に落とし、もはや身を起こす力も無く倒れ込んでいるマリアノの頭頂部を、ベルムデスは荒っぽく掴んだ。
そして、強引に、先刻のスペイン人の男たちの前まで引き摺ってくると、床にその額をこすりつけるようにして土下座をさせる。
それから、己自身も再びその脇に深々と土下座をし、幾度も、幾度も、謝った。
「申し訳ございません!!
この通りでございます!!
どうかお赦しを…。
せがれのしたことは…弁償を…金は、今晩の宿代をはたいてでも、旦那様にお返しいたします!!」
ベルムデスは平伏しながら、隣りで倒れ込むようになったまま強引に土下座させられている「せがれ」の頭を、さらに床に強く押し付けて、怒鳴りつけた。
「おまえも、謝らんか!!
この出来損ないめ!!」
だが、少年は、もはや完全に憔悴し切っており、頭を押さえ付けられた土下座の姿勢のまま、その意識が保たれているのかさえ定かではない。
ベルムデスの、その大袈裟とも取れるほどの剣幕と恐縮ぶり、そして、死んだように動かなくなってしまった少年の様子に、その場の者たちは目を奪われ、トゥパク・アマルの息子のこと、そして、少年の風貌のことからは、いつしか意識を外(はず)していた。
部屋の四隅で、ぐっと息を詰めて見守るマリアノの護衛官たちは、ベルムデスの対応で急場を凌げたかと深く胸を撫(な)で下ろしながらも、本当に負傷していると見られるマリアノの状態を、それはもうハラハラと案ぜずにはおられない。
一方、下層のインカ族の男たちが大勢を占めていたその場の傍観者の客たちは、今は、むしろ、同族の物乞いの親子、特に、「父親」からの激しい叱責に打ちのめされたようになっている少年に同情的な顔色になって、スペイン人の男たちの出方を探るような眼で見ている。
その場の空気は、その少年を大目に見てやれよ、という気配に変っていた。
マリアノをどやしつけていたスペイン人の当該の男は、己に向けられる冷ややかな周囲の視線を感じ取ると、憎々しげに唇を歪めた。
そして、蔑むように、その哀れな物乞い風情の親子たちを見下ろし、チッと二人に向かって唾を吐く。
「おまえたちのような落ちぶれた者から金を取るほど、俺は終わっちゃいない」
彼は、荒っぽくスペイン語で毒づくと、仲間たちに、「興ざめした。店を変えようぜ」と目配せをして、出て行った。
他方、二人がまだ土下座をしている中、他の客たちも、彼らに向けていた視線を外し、店の中には元の賑わいが戻っていく。
場の空気の変わったことを察知したベルムデスが、慎重に顔を上げる。
そして、マリアノの頭を床に押し付けていたその手で、被り物をかけ直す振りをしながら、人目に触れぬよう、そっと少年の頭を撫でた。
その指が、今は大きく震えている。
(マリアノ様…――申し訳ございません!!
……こうするしかなかったのです!!)
マリアノは、呆然と頭を上げながら、被り物の陰からベルムデスを虚ろに見上げた。
ベルムデスの連打によって見る影も無いほどに腫れ上がったマリアノの顔の、その唇の両端からは真紅の血が滴り、そして、その瞳からは、大粒の涙が、とめどなく溢れ続けている。
(母上が…兄上が…フェルナンドが…――!!)
「!!」
離れた席にいて、先ほどのスペイン人たちの会話の内容までは聞こえていなかったベルムデスは、今、マリアノの瞳の色を見て、瞬時に、何が起きたのかを悟った。
(マリアノ様…――!!)
ベルムデスは、即座に、物陰にマリアノを連れて行くと、その腕にマリアノを強く抱き締める。
マリアノは倒れるように、ベルムデスの胸の中に身を沈めた。
一連の出来事を息詰めて見ていたウェイターは、とりあえず事が収まったことに、深く安堵していた。
あのまま客が暴れ出して、店の物を壊すだの、喧嘩だのに発展してはたまらぬ、と、気が気ではなかったのだ。
彼は、再び、いかにも迷惑そうに、マリアノたちを一瞥した。
「…ったく、言わんこっちゃない。
厄介ごとを起こしやがって」
そう呟いて、忌々(いまいま)しげに舌打ちしながら溜息をつく。
ウェイターの目には、今、物陰で、ひしと抱き合っているその「親子」の様子は、スペイン人たちから端金(はしたがね)を巻き上げられずにすんだことを喜び合っている、さもしい姿に見えていたことだろう。
一方、ベルムデスは食事どころではなく、マリアノを伴い、急いで宿の部屋へと戻った。
そして、母や兄弟の捕われたことによる激しいショック状態にあるマリアノを、宥(なだ)めながらベッドに横たえた。
それから、彼自身は、ひどく険しい目つきで足早に宿を出ると、影武者たちを呼び寄せ、ミカエラらの安否に関する正確な情報を集めるよう、俊敏に指示を送る。
影武者たちの急ぎ去り行く姿を見やりながら、彼もまた衝撃を隠せぬ眼差しで愕然と呻いた。
「まさか…ミカエラ様…――イポーリト様…フェルナンド様までが…捕われたなどと…!!」
彼自身も激しい打撃を受けながらも、だが、ベルムデスは、その心を休める間など無く、再び、急ぎ足で宿にとって返した。
そして、素早く、出立の準備を整える。
ミカエラや二人の息子たちまでが囚われた今、マリアノの存命は、ただならぬ重要性を帯びていた。
その上、先ほどの食堂の出来事を、何者が見ており、いかなる疑念を抱いたかも分からない。
この場に長居は危険だった。
夜間の旅は、それこそ危険ではあったが、ここに残って追っ手に囚われては元も子も無い。
彼ら一行は夜明けを待たずに、その宿を後にした。


